
補聴器の購入を考えたとき、「補聴器で評判の良いメーカーはどこだろう?」と探し始める方は非常に多いです。
インターネットで調べると、「使って良かった」という口コミがある一方で、「リオネット補聴器の評判が悪い」といった気になる情報も見つかり、一体何を信じれば良いのか分からなくなってしまいますよね。
日本で1番売れている補聴器メーカーや、リオン補聴器の評判、そして補聴器メーカーの日本一覧など、知りたい情報は山ほどあるはずです。
また、世界の補聴器の5大メーカーの比較や、一部で話題になる天皇陛下が愛用している補聴器のメーカーについても気になるところでしょう。
そもそも補聴器の平均的な値段はいくらなのか、そして最も重要な失敗しないための選ぶポイントは何なのか。
この記事では、そのような数々の疑問に専門的な視点からお答えし、あなたに最適な一台を見つけるための道筋を分かりやすく解説します。
◎この記事で分かること
- 評判の良い補聴器メーカーの世界と日本の主要企業がわかる
- 各メーカーの具体的な特徴や価格相場を比較できる
- 自分に合った補聴器選びの重要なポイントが明確になる
- 購入後の後悔を避けるための注意点が理解できる
補聴器で評判の良いメーカーを探す前に知るべきこと

世界の補聴器の5大メーカーは? 比較して解説

補聴器の世界市場は、実は一部の巨大メーカーグループによって大部分のシェアが占められています。
「5大メーカー」と尋ねられることが多いですが、現在では主に6つの大手メーカー(ブランド)が世界市場を牽引していると理解するのが正確です。
これらのメーカーは、長年にわたる研究開発で培われた高い技術力と豊富な製品ラインナップを誇り、世界中の人々の聞こえを支えています。
まずは、その6大メーカーの概要を一覧で見てみましょう。
| メーカー(ブランド)名 | 国 | 特徴 |
|---|---|---|
| オーティコン (Oticon) | デンマーク | 「脳で聴く」をコンセプトに、脳への負担を軽減する自然な聞こえを追求。AI技術も積極的に導入。 |
| シグニア (Signia) | ドイツ | シーメンス社の流れを汲む。強力な雑音抑制機能や、スタイリッシュなデザインに定評がある。 |
| フォナック (Phonak) | スイス | 世界シェアNo.1を誇る。子供から大人まで、あらゆる難聴に対応できる幅広い製品と高い技術力が強み。 |
| スターキー (Starkey) | アメリカ | オーダーメイドの耳あな型に定評。AIによる健康管理機能など、先進的な機能の搭載に積極的。 |
| リサウンド (Resound) | デンマーク | スマートフォンとの連携機能をいち早く開発。自然な聞こえと手厚い保証制度が魅力。 |
| ワイデックス (Widex) | デンマーク | 「自然な音質」へのこだわりが強く、特に音楽を愛好するユーザーからの評価が高い。 |
このように、メーカーごとに独自の哲学や強みがあります。
例えば、騒がしい場所での会話が多い方はシグニアやフォナック、音楽を楽しみたい方はワイデックス、脳の疲れを軽減したい方はオーティコンといったように、ご自身のライフスタイルに合わせてメーカーの得意分野を参考にすることが、良い補聴器選びの第一歩となります。
ポイント
世界市場の補聴器は、スイス、デンマーク、ドイツといったヨーロッパのメーカーが非常に強い力を持っています。
これは、古くから精密機器産業や福祉に対する意識が高かった歴史的背景が関係していると言えるでしょう。
日本で1番売れている補聴器メーカーはどこ?
日本国内において、最も高いシェアを誇り、1番売れている補聴器メーカーは「リオネット補聴器」です。
リオネット補聴器は、リオン株式会社が製造・販売する日本のブランドで、国内シェアのトップを長年維持しています。
その理由は、日本の市場に深く根差した製品開発と販売戦略にあります。
日本の聞こえと環境に合わせた製品開発
リオネット補聴器は、「日本の言葉の聞き取りやすさ」や「日本の高温多湿な気候」を考慮した製品開発を行っています。
例えば、湿気や汗による故障を防ぐための防水・防塵機能の強化や、日本語特有の母音・子音の響きを解析した音質調整などが挙げられます。
このような国内メーカーならではの細やかな配慮が、多くのユーザーから支持される理由の一つです。
全国を網羅する手厚い販売・サポート網
もう一つの強みは、全国各地に広がる販売店のネットワークです。補聴器は購入後の調整(フィッティング)やメンテナンスが非常に重要になります。
リオネット補聴器は、都市部だけでなく地方においても手厚いサポートを受けやすい体制を整えているため、特にご高齢の方でも安心して利用できるというメリットがあります。
国内メーカーの安心感は大きな魅力ですが、だからと言って海外メーカーが劣るわけではありません。
むしろ、最新技術の開発スピードやグローバルなデータに基づいた音質設計では、世界6大メーカーに分があることも多いです。
メーカーの国籍にこだわらず、広い視野で比較検討することをおすすめします。
日本の代表的な補聴器メーカーの一覧
世界6大メーカーや国内トップのリオネット補聴器以外にも、日本にはいくつかの補聴器メーカーが存在します。
それぞれに特徴があり、特定のニーズに応える製品を開発しています。ここでは、代表的な日本のメーカーをいくつかご紹介します。
リオン株式会社(リオネット補聴器)
前述の通り、国内シェアNo.1のメーカーです。「Made in Japan」の品質と信頼性、そして全国的なサポート体制が最大の強み。
幅広い価格帯の製品を揃え、多くの人々の聞こえを支えています。
パナソニック補聴器
大手電機メーカーであるパナソニックも補聴器を開発・販売しています。
特に、集音器と補聴器の中間に位置するような、比較的軽度の難聴者向けの製品や、操作の分かりやすさを重視した製品に特徴があります。
家電製品で培った技術力とブランドの安心感が魅力です。
コルチトーン補聴器株式会社
1956年創業の歴史ある補聴器専業メーカーです。
オーダーメイド補聴器に強みを持ち、一人ひとりの耳の形や聞こえに合わせた製品づくりで定評があります。
長い歴史の中で培われたノウハウと技術力が特徴です。
豆知識:海外メーカーの日本法人
オーティコンやシグニアといった世界6大メーカーも、日本国内に「日本法人」を設立して事業を展開しています。
そのため、海外メーカーでありながら、日本の薬機法(旧薬事法)に基づいた承認を得ており、サポート体制も国内で完結しています。
購入後のアフターサービスで不安を感じる必要はほとんどありません。
これらのメーカーから自分に合ったものを選ぶには、やはりそれぞれの製品を実際に試聴し、比較することが不可欠です。
まずは、これらのメーカーを扱っている補聴器専門店に相談してみましょう。
補聴器の平均的な値段はいくらですか?

補聴器の値段は、多くの方が最も気にするポイントの一つですが、その価格は片耳でおおよそ5万円から60万円以上と、非常に幅広いのが実情です。
両耳で購入する場合は、単純に2倍の価格が目安となり、一般的には30万円から100万円を超えるケースも珍しくありません。
なぜこれほど価格に差があるのかというと、その理由は搭載されている「機能」と「性能」の違いにあります。
高価な補聴器ほど、より高度な機能が搭載されており、様々な環境で快適な聞こえを提供してくれます。価格帯による性能の違いを簡単にまとめると、以下のようになります。
| 価格帯(片耳) | 主な性能・機能 | おすすめする人 |
|---|---|---|
| 10万円前後 | 基本的な増幅機能が中心。騒音抑制機能はシンプル。 | 主に自宅など静かな環境で、1対1の会話が中心の方。 |
| 20万円~30万円 | 雑音と会話をある程度自動で判別。基本的な指向性機能。 | 日常生活の様々な場面で装用し、複数の人との会話も楽しみたい方。 |
| 40万円以上 | AIによる高度な環境認識。強力な雑音・風切り音抑制。スマホ連携や充電機能などが充実。 | 会議や会食、旅行など、アクティブに活動し、騒がしい場所でもクリアな聞こえを求める方。 |
注意点
「高ければ高いほど良い」と一概には言えません。
例えば、普段ほとんど外出せず、静かなご自宅で過ごすことが多い方が最高性能のモデルを購入しても、その機能を十分に活かせない可能性があります。
ご自身のライフスタイルや、聞こえに困っている場面を専門家に具体的に伝えることが、過不足のない適切な価格帯の補聴器を選ぶ上で非常に重要です。
また、補聴器の購入には、条件を満たせば国や自治体の補助金制度を利用できる場合があります。
購入を検討する際には、お住まいの市区町村の福祉課などに問い合わせてみることをお勧めします。
「使って良かった」口コミを参考にする注意点

補聴器を選ぶ際、インターネットや知人からの「このメーカーは使って良かった」という口コミは、非常に魅力的に聞こえます。
しかし、これらの口コミを参考にする際には、いくつか注意すべき点があります。
結論から言うと、口コミはあくまで個人の感想であり、絶対的な評価ではないと理解することが重要です。
なぜ口コミの鵜呑みは危険なのか
その最大の理由は、「聞こえ」の状態が一人ひとり全く異なるからです。
同じ「聞こえにくい」という悩みでも、どの高さの音が聞き取りにくいのか(聴力レベル)、言葉の聞き分け能力はどの程度か、といった状態は千差万別です。
例えば、Aさんがある補聴器を使って「騒がしい場所でも会話がクリアになった」と感じたとしても、Aさんとは聴力レベルが異なるBさんが同じ補聴器を使っても、同様の効果が得られるとは限りません。
むしろ、音が響きすぎて不快に感じてしまう可能性すらあります。
口コミを有効に活用するポイント
では、口コミは全く役に立たないのかというと、そうではありません。
参考にする際は、以下のような視点を持つと良いでしょう。
- 具体的な使用場面:「会議で役立った」「テレビの音が聞きやすくなった」など、どんな場面で良かったのかを確認する。
- デザインや操作性:「小さくて目立たない」「電池交換がしやすい」といった、音質以外の物理的な特徴に関する感想は参考にしやすいです。
- 販売店の対応:「お店の人が親身に相談に乗ってくれた」といった、製品そのものではなく、購入したお店に関する評判は非常に参考になります。
最も信頼できる「評価」とは?
補聴器選びで最も信頼できる評価は、あなた自身の耳で「試聴」したときの感覚です。
評判の良いメーカーの情報を参考にしつつも、最後は必ず認定補聴器技能者などの専門家がいるお店で相談し、ご自身の耳で実際の聞こえを確かめてから決定するようにしてください。
特定の補聴器で評判の良いメーカーと選ぶ注意点

国内シェア1位、リオン補聴器の評判

国内で最も多くの人に選ばれているリオン(リオネット補聴器)ですが、その評判はどのようなものなのでしょうか。
多くのユーザーから支持されている点と、一部で聞かれる懸念点の両面から見ていきましょう。
良い評判・高く評価されている点
リオン補聴器が評価されている最大のポイントは、やはり日本のユーザーに寄り添った製品づくりとサポート体制です。
具体的には、以下のような点が挙げられます。
- 安心の国内生産:品質管理が行き届いた国内工場で生産されていることへの信頼感。
- 湿気への強さ:日本の高温多湿な気候を考慮し、汗や湿気に強い防錆・防水設計に力を入れている点。
- 全国的なサポート網:何かあった時に、家の近くの販売店で相談しやすいという利便性。
- 操作の分かりやすさ:特にご高齢のユーザーを意識した、シンプルで扱いやすいモデルが豊富な点。
これらの点から、「初めての補聴器でも安心して使えた」「購入後のメンテナンスが楽で助かる」といった声が多く聞かれます。
一部で見られる懸念点
一方で、一部のユーザーからは「音が少し機械的」「デザインの選択肢が少ない」といった声が聞かれることもあります。
これは、海外の大手メーカーがAI技術を駆使したより自然な音質処理や、デザイン性の高いモデルを次々と発表していることとの比較からくる意見かもしれません。
音質の好みは人それぞれ
補聴器の「音質」は、非常に主観的な要素が強い部分です。
リオンのハッキリとした音作りを好む方もいれば、海外メーカーのより自然で柔らかい音作りを好む方もいます。
これは優劣の問題ではなく、個人の好みや聞き慣れた音の傾向が大きく影響します。だからこそ、実際に聞き比べてみることが何よりも大切なのです。
リオネット補聴器の評判が悪いという噂の真相

インターネットで検索すると、「リオネット補聴器 評判 悪い」といった関連キーワードが表示されることがあり、不安に感じる方もいるかもしれません。
しかし、これは必ずしも製品自体の品質が悪いことを意味するわけではありません。
このようなネガティブな評判が出てしまう背景には、いくつかの複合的な理由が考えられます。
理由1:ユーザー数が圧倒的に多い
最も大きな理由として、リオネット補聴器は国内シェアNo.1であり、ユーザーの母数が非常に多いことが挙げられます。
利用者が多ければ多いほど、それに比例して「自分には合わなかった」と感じる人の絶対数も増えるのは自然なことです。
満足している多くの声は表に出にくい一方で、不満の声はインターネット上で目立ちやすい傾向があります。
理由2:調整(フィッティング)が合っていない
補聴器は、購入したままの状態で最高のパフォーマンスを発揮するわけではありません。
使用者の聴力に合わせて音を細かく調整する「フィッティング」という工程が極めて重要です。
このフィッティングが不十分だと、どんなに高性能な補聴器でも「うるさい」「言葉が聞き取れない」といった不満につながってしまいます。
悪い評判の中には、製品の問題ではなく、販売店の技術力や調整不足が原因であるケースが少なくありません。
理由3:ユーザーの期待値とのギャップ
「補聴器を着ければ、昔のように何でも完全に聞こえるようになる」という過度な期待を持っていると、実際の聞こえ方とのギャップにがっかりしてしまうことがあります。
補聴器はあくまで「聞こえを補助する」医療機器であり、失われた聴力を完全に取り戻す魔法の道具ではありません。
この点に関する購入前の説明が不足していると、不満の原因となり得ます。
重要なのは「どこで買うか」
これらの理由からわかるように、補聴器の満足度は、製品そのものだけでなく、「誰から、どこで買うか」に大きく左右されます。
信頼できる知識と技術を持った専門家がいる販売店を選ぶことが、悪い評判のような失敗を避けるための最も確実な方法です。
天皇陛下が愛用している補聴器のメーカーとは
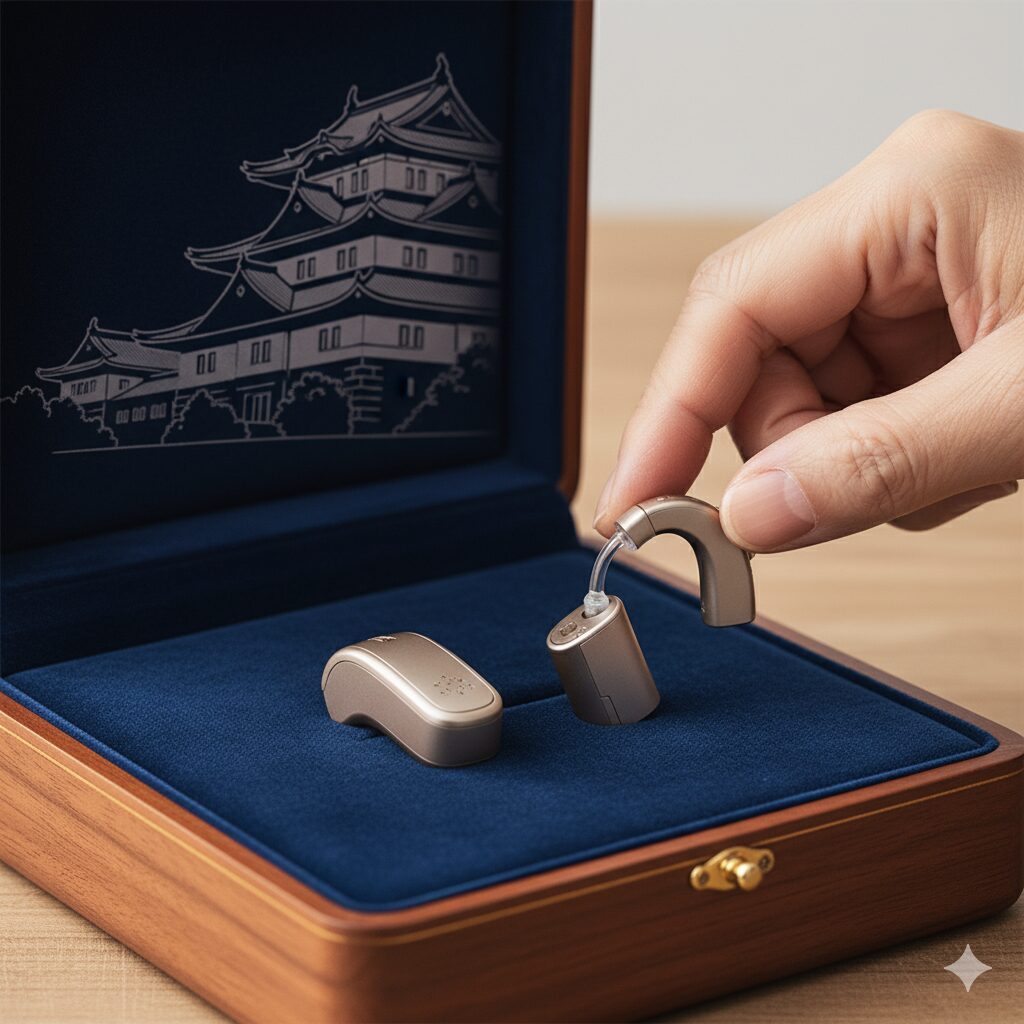
「天皇陛下や皇室の方々が、どのメーカーの補聴器を使用されているのか」という点は、多くの方が関心を持つ事柄のようです。
その品質や信頼性の証として、参考にしたいと考えるお気持ちはよく分かります。
しかしながら、結論から申し上げますと、上皇陛下や今上天皇陛下を含め、皇室の方々が具体的にどのメーカーのどの機種を使用されているかという公式な発表はありません。
これはプライバシーに関わる情報であり、宮内庁やメーカーから公表されることは基本的にありません。
一部のメディアやインターネット上で憶測が語られることもありますが、それらはあくまで推測の域を出ない情報です。
補聴器選びで本当に大切なこと
特定の著名人や権威ある方が使用しているという事実は、確かに安心材料の一つになるかもしれません。
しかし、繰り返しますが、補聴器選びで最も優先すべきは、ご自身の聴力、ライフスタイル、そして予算に合っているかどうかです。
他の誰かにとって最高の補聴器が、あなたにとっても最高であるとは限りません。
世間の評判や使用実績はあくまで参考情報の一つと捉え、ご自身の耳で確かめることを大切にしてください。
信頼できるメーカーの製品であれば、どれも高い品質基準をクリアしています。
大切なのは、その中からご自身に最適な一台を、専門家と共にじっくりと選んでいくプロセスです。
失敗しない補聴器を選ぶポイント

評判の良いメーカーの知識を得ることも大切ですが、最終的に補聴器選びで失敗しないためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、後悔しないために必ず実践していただきたいポイントを解説します。
1. まずは耳鼻咽喉科を受診する
聞こえにくさを感じたら、自己判断で補聴器販売店に行く前に、必ず「補聴器相談医」の資格を持つ耳鼻咽喉科の医師に相談しましょう。
聞こえにくさの原因が、治療で改善する病気(中耳炎など)や耳垢の詰まりである可能性もあるからです。
まずは医学的な診断を受け、本当に補聴器が必要な状態かを判断してもらうことが全ての始まりです。
2. 信頼できる販売店を選ぶ
補聴器の満足度を左右する最大の要因は、販売店の質です。
「認定補聴器技能者」という専門資格を持つスタッフが在籍しているかどうかは、信頼できるお店を見分ける重要な指標になります。
彼らは聴覚に関する専門知識と豊富な経験を持ち、あなたの聞こえの状態や生活環境に合わせた最適な器種選びと、丁寧なフィッティングを行ってくれます。
3. 聴力とライフスタイルを正確に伝える
専門家とのカウンセリングでは、ご自身のことをできるだけ詳しく伝えましょう。
「会議での聞き取りに困っている」「家族とのテレビ鑑賞を楽しみたい」「趣味のコーラスで音程が取りづらい」など、具体的にどのような場面で困っているかを伝えることで、専門家はあなたに必要な機能や性能を的確に判断できます。
4. 必ず「試聴」と「貸し出し」を利用する
店内での短い試聴だけでなく、実際に普段の生活環境で補聴器を使ってみる「試聴貸し出しサービス」を必ず利用してください。
自宅でのテレビの音、家族との会話、近所のスーパーでの騒音など、日常の様々な場面で聞こえ方を試すことで、その補聴器が本当に自分に合っているかを冷静に判断できます。
多くの販売店では、無料または少額で貸し出しを行っています。
焦りは禁物です。特に初めての補聴器選びでは、すぐに購入を決める必要は全くありません。
複数のメーカーの機種を試し、じっくり比較検討する時間を取りましょう。
信頼できる販売店であれば、あなたが納得するまで親身に付き合ってくれるはずです。
補聴器の評判の良いメーカー探しと試聴の重要性
この記事では、評判の良い補聴器メーカーに関する情報から、具体的な選び方のポイントまでを解説してきました。
最後に、あなたが最適な一台にたどり着くための重要な要点をまとめます。
補聴器について詳しく知った上で、「自分にはまだ早いかな?」「まずはもっと手軽なものから試したい」と感じた方へ。
最近では、聞こえに不安を感じ始めた方向けに、イヤホンのようなデザインで使いやすい高性能な集音器も人気です。
補聴器とは異なる選択肢として、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。


